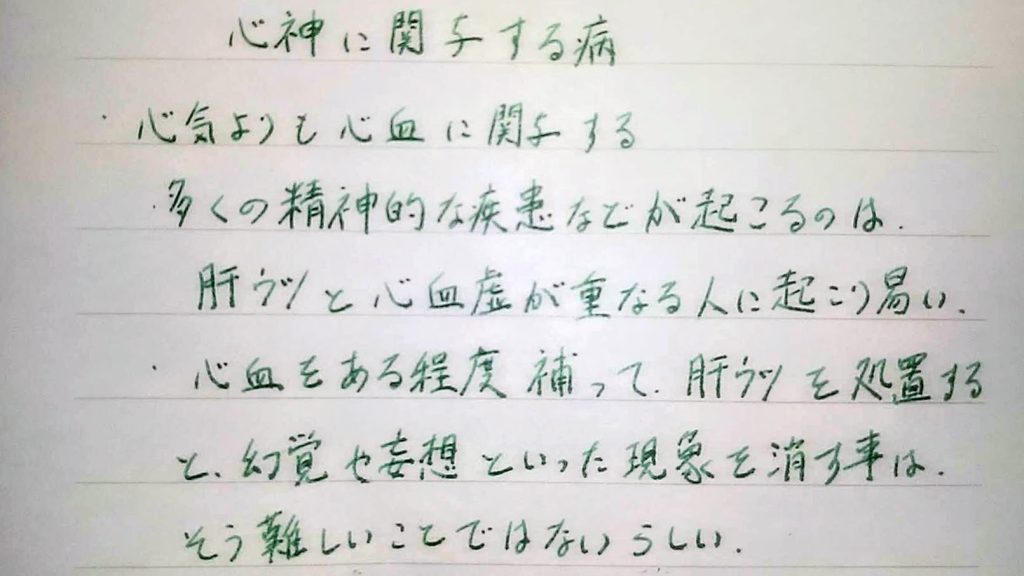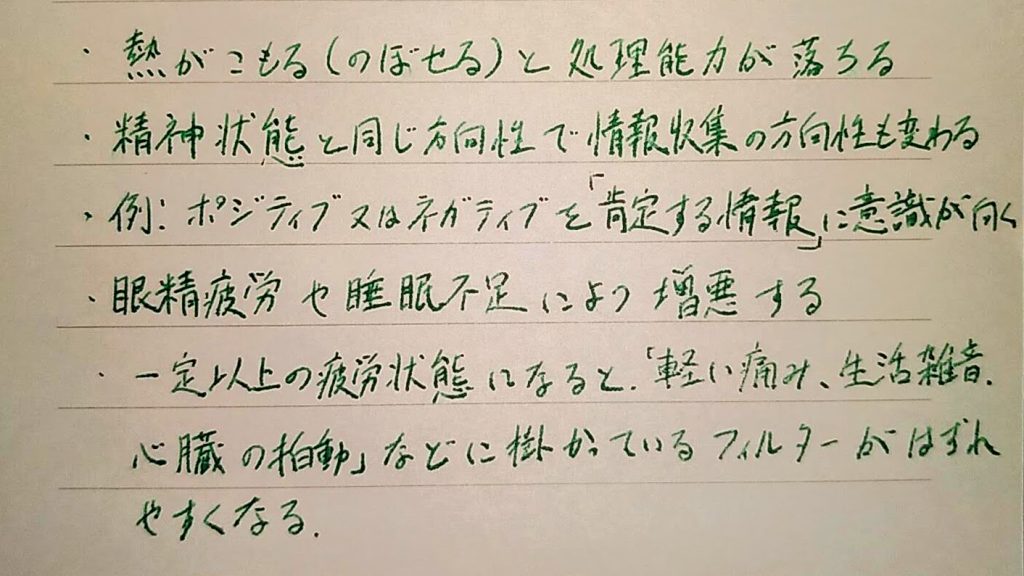| ・水痘・帯状疱疹ウイルスによって引き起こされる、神経に沿って現れる皮膚疾患 |
| ・一度かかった水痘(=水ぼうそう)は本来、生涯免疫として抑え込まれている |
| ・体内に潜伏したものが、免疫低下時に再活性化して発症する |
発症のきっかけになる免疫力低下は以下のようなもの
- 体力消耗(ストレス・過労・睡眠不足)
- 病後や手術後
- 季節の変わり目
- 加齢(特に50代以降)
- 持病や免疫抑制薬の使用
ウイルスの再活性化を防ぐには、免疫力を保つ日常管理がとても重要です
最初に出てくるのは前駆症状で
- ピリピリ・チクチクする痛み
- かゆみ、熱感
- 皮膚に違和感(でも発疹は無い)
これらの数日後に帯状の発疹(水泡や発赤)が出ます
れを逃すと神経痛(帯状疱疹後神経痛)が残りやすくなります
でも…
- 見逃す
- 忙しくて受診が遅れる
- 皮膚病だと思って様子を見る
・ ・ ・ などで遅れてしまうことが あり、治った後のほうが辛くなるという人が多いのが現状のようです ※しかも神経痛が数ヶ月~年単位で残る
当院では…
初期は遠隔からの全身調整、該当の神経帯を根部と末端で挟んで低周波通電 2Hz(10~15分)、 発疹周囲を囲むようにお灸をします。 どうしても箇所が多くなるので電気温灸器を使用 (49度以上の設定が多い)。 皮膚症状が落ち着いてきたら周辺から徐々に筋膜リリースを加えます。
帯状疱疹が顔面部に出た場合は特に慎重を要します。 三叉神経痛を後遺症移行前に併発することあり、この場合は早い段階から患者本人も触りたがらず、かえって接触刺激に過敏になってしまいます。何にしろ、ファッシアの重層化(癒着状態が神経膜を巻き込んでの滑走障害)がある程度(むしろがっつり?)残るので。筋膜リリースは必須といえます。ただし周辺部から。
※局所がどうしても触れない!というほど接触痛が強い場合&症状が長期化している場合
該当の変動経の通る指に 末節骨~中手(足)骨のゆがみを整復する。 方法は各骨の長軸に対して回旋してみて”緩んでいる”ほうへじんわり捻じります。捻じってる最中から痛みに変化が見られます。